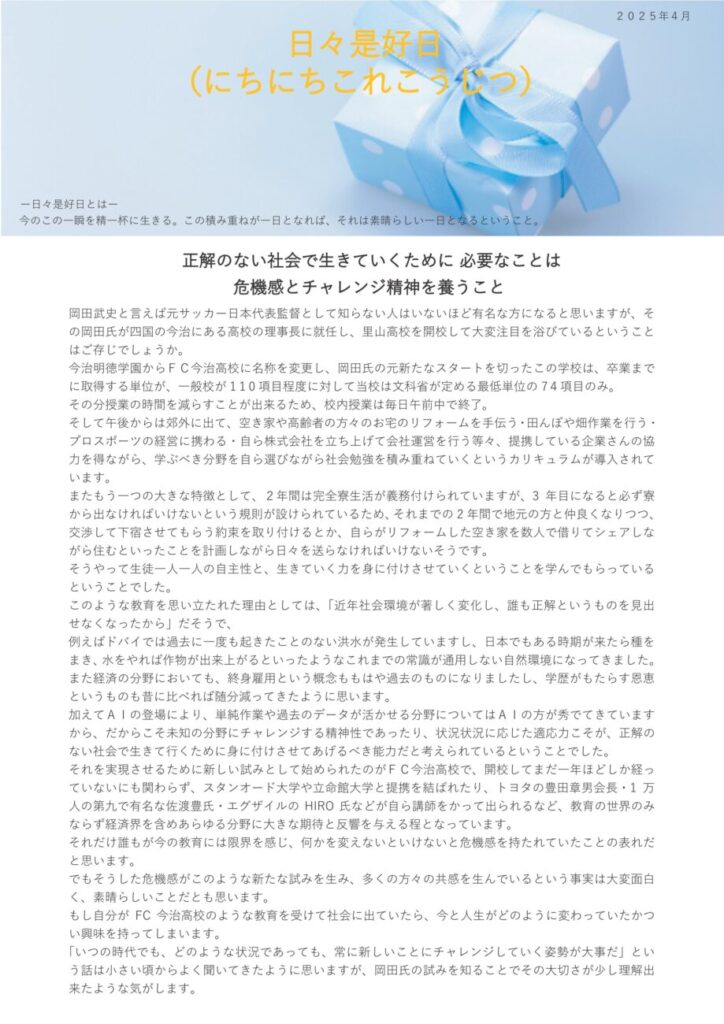
岡田武史と言えば元サッカー日本代表監督として知らない人はいないほど有名な方になると思いますが、その岡田氏が四国の今治にある高校の理事長に就任し、里山高校を開校して大変注目を浴びているということはご存じでしょうか。
今治明徳学園からFC今治高校に名称を変更し、岡田氏の元新たなスタートを切ったこの学校は、卒業までに取得する単位が、一般校が110項目程度に対して当校は文科省が定める最低単位の74項目のみ。
その分授業の時間を減らすことが出来るため、校内授業は毎日午前中で終了。
そして午後からは郊外に出て、空き家や高齢者の方々のお宅のリフォームを手伝う・田んぼや畑作業を行う・プロスポーツの経営に携わる・自ら株式会社を立ち上げて会社運営を行う等々、提携している企業さんの協力を得ながら、学ぶべき分野を自ら選びながら社会勉強を積み重ねていくというカリキュラムが導入されています。
またもう一つの大きな特徴として、2年間は完全寮生活が義務付けられていますが、3年目になると必ず寮から出なければいけないという規則が設けられているため、それまでの2年間で地元の方と仲良くなりつつ、交渉して下宿させてもらう約束を取り付けるとか、自らがリフォームした空き家を数人で借りてシェアしながら住むといったことを計画しながら日々を送らなければいけないそうです。
そうやって生徒一人一人の自主性と、生きていく力を身に付けさせていくということを学んでもらっているということでした。
このような教育を思い立たれた理由としては、「近年社会環境が著しく変化し、誰も正解というものを見出せなくなったから」だそうで、
例えばドバイでは過去に一度も起きたことのない洪水が発生していますし、日本でもある時期が来たら種をまき、水をやれば作物が出来上がるといったようなこれまでの常識が通用しない自然環境になってきました。
また経済の分野においても、終身雇用という概念ももはや過去のものになりましたし、学歴がもたらす恩恵というものも昔に比べれば随分減ってきたように思います。
加えてAIの登場により、単純作業や過去のデータが活かせる分野についてはAIの方が秀でてきていますから、だからこそ未知の分野にチャレンジする精神性であったり、状況状況に応じた適応力こそが、正解のない社会で生きて行くために身に付けさせてあげるべき能力だと考えられているということでした。
それを実現させるために新しい試みとして始められたのがFC今治高校で、開校してまだ一年ほどしか経っていないにも関わらず、スタンフォード大学や立命館大学と提携を結ばれたり、トヨタの豊田章男会長・1万人の第九で有名な佐渡豊氏・エグザイルのHIRO氏などが自ら講師をかって出られるなど、教育の世界のみならず経済界を含めあらゆる分野に大きな期待と反響を与える程となっています。
それだけ誰もが今の教育には限界を感じ、何かを変えないといけないと危機感を持たれていたことの表れだと思います。
でもそうした危機感がこのような新たな試みを生み、多くの方々の共感を生んでいるという事実は大変面白く、素晴らしいことだとも思います。
もし自分がFC今治高校のような教育を受けて社会に出ていたら、今と人生がどのように変わっていたかつい興味を持ってしまいます。
「いつの時代でも、どのような状況であっても、常に新しいことにチャレンジしていく姿勢が大事だ」という話は小さい頃からよく聞いてきたように思いますが、岡田氏の試みを知ることでその大切さが少し理解出来たような気がします。
