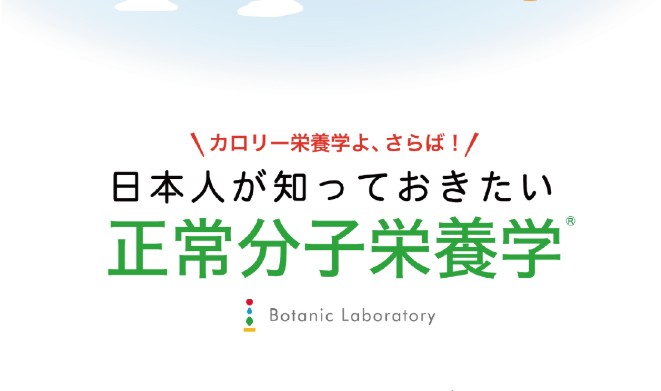日本は「糖質」「脂質」「タンパク質」の3つの栄養素の摂取量バランスをコントロールするカロリー(エネルギー)栄養学が主流になっていますが、世界の主流はこの3つの栄養素に「ビタミン」「ミネラル」を加えた5大栄養素の摂取量調整を行う分子栄養学(分子整合栄養医学)になります。
なぜならこの5種類の栄養摂取バランスを調整していく事で、病気や不具合を未然に防いだり、回復に繋がりやすくなることが確認されているからです、
ではそうした効果が期待できるというエビデンスはどのように取られ、どのように纏め上げられたのかというと、そこには二人の人物が大きく関わったと言われています。
一人はアデル・デービスというアメリカの女性管理栄養士です。
なぜこのような思い付きに至ったのか、どのようにしてそのような取り組みを行えたのかという詳細については不明ですが、彼女は大学病院のドクターの協力を得ながら、様々な症状を抱える約20000人の患者さんにあらゆる栄養素を与えつつ、それによって病状がどう変化していくか細かく観察。
それを殴り書きのようにして膨大な資料を作成したそうです。
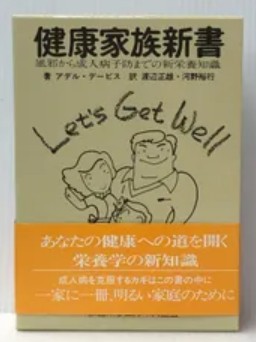
現在でもアマゾンなどで古書での入手が可能です。
そしてその資料をどのような経緯で入手されることになったのかはこれまた不明ですが、単独としては唯一ノーベル賞を二度受賞し、ビタミンCの大量摂取を推奨されていることで世界的に有名なライナス・ポーリング博士が資料の内容を纏めて体系化したと言われています。
それが分子栄養学(分子整合栄養医学)になります。
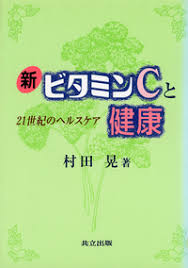
基本的にはカロリー栄養学しか活用していない日本でも、サプリメントの設計を行う際に活用されることがありますし、また厚労省が推奨している糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルの一日の摂取量目安も、おそらくは分子栄養学を参考に決められていると思われます。
そして分子栄養学が確立されたのは今から40年以上も前のことになりますから、現在ではこれら5つの栄養素に加え、ファイトケミカル(植物色素)とハーブを合わせた7大栄養素による栄養調整が世界での主流になりつつあります。